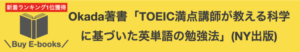Hey. Fukuoka English GymのOkadaです。
私は72時間ルールを設けています。
何かをしようかなあ〜と思ったら、72時間以内に行動を起こす、というものです。3日坊主という言葉もあるように脳科学では72時間というのはパフォーマンスの影響が起きる時間と言われているため信憑性が高い時間なんですね。そして、社長の多くがこのルールを実践しているというデータ、そして、尊敬している企業の経営者が実践しているというのを知り、(自分も経営者として、)これやろう!って決めて、具体的には、1 プラニングを立てる 2 実際に行動を起こす のいずれかでルール達成、というようにしています。
私の経験でしかないですが、このルールに基づいたものはほぼ全て、失敗したとしても、経験値になっているな、と振り返っても感じます(その当時はやるんじゃなかった〜って思うんですけどね)。実際に行動にうつしてみる、っていうのは本当に難しいけど、自分の中で大きなものが蓄積された、っていう感覚になります。
さて、今回はKフリークにとってワクワクするトピックです。NPR(アメリカの公共ラジオ)でYale大学の教授のインタビューを先月聞いて、なるほど〜となりましたのでご紹介します。
Yale 大学の実験:BTSの"Boy with Luv"の基本ステップをダンスできるか
認知バイアスについて研究をされているYale大学の心理学の教授 Woo-kyoung Ahn さんが、「人が自分自身を過大評価する傾向があるのかを実証する」実験を行いました。
実験の内容:BTSの"Boy with Luvの一部を視聴させ、実際に踊らせる
具体的には、BTSの"Boy with Luv"↓の一部の映像を学生に何度も視聴させ、その後実際にダンスをさせてみるというものです。
MVの中で最も簡単な6秒間を何度も視聴させ、その後、自分は絶対できるという自身がある学生にダンスさせてみる。
結果:全員失敗
すると、実際にやってみた全員が失敗した。というとてもシンプルな実験です。これは"fluency effect"という認知バイアスで、人が簡単そうにやっていることは自分もできると過信してしまう、というものです。
英語学習でいえば、とても授業は上手な先生に教わると、深い理解ができて、理解=実際に使える、と過信してしまうため、復習をおろそかにしてしまう、というところですね。だから、私Okadaは復習をさせるための仕掛けや声掛けは受講生にかなり行います。
NPRの教授のインタビュー音声
教授のインタビューの音声はこちらでです。
https://www.npr.org/transcripts/1122660697
トランスクリプトもついています。大学入試でいうと、東京外国語大でもリスニング問題の出典になっているNPRですので、聞き取りはかなりしやすいですよ。
実験から分かる認知バイアスと対策法
インタビューでは3つの認知バイアスが紹介されています。
いずれによせ、進化論的な視点で考えると仕方ないもの、昔は捕食動物たちがいたりと厳しい環境の中で生き残るために私たちの祖先は「素早い決断を下す」必要があった。それが「自分は絶対できる」という過信にもつながっている、
①過大評価する傾向がある
"illusion of fluency"という心理学領域で有名な考えです。人が上手に何かをしているのを目にすると、それは努力なんかしてないように見えてしまい、そうなると、自分もそこまで努力しなくてもできるだろう、という思考になってします。
①過大評価の対策
実際にやってみる。
何を実行する前にオーバーなくらい準備をしておく。起こりそうな問題点についても考えておく。
実際にやってみる。これに尽きるじゃないかな、と最近痛感しています。私が72時間ルールを設定しているのも、おそらく心のなかで、何らかのバイアスの影響を受けると思っていたのかもしれないな、とすごく腑に落ちました。
②ネガティブにひっぱられる
研究によれば、"negative bias"という、positiveとnegativeな出来事が同数あったとしたら、negativeな方を重視してしまう、という傾向があるというものです。この人間の特性は、間違った選択をすることにもつながるので危険をはらんでいる。
②ネガティブの対策
何らかの選択をする時には、選択肢の中でポジティブな部分を意識してしっかりみてみる。枠組みをひっくり返してみる。
例. 食品のパッケージ(例. ひき肉):「脂肪11%」→「赤身89%(脂肪の少ない部分89%)」
就活の自己分析のような感じですね。 「おとなしい」→「物事を慎重に考えられる」 「うるさい」→「周りを巻き込める」 ちなみに、周りに嫌な人や妬みの対象がいる場合、その人の中の「リスペクト」できる部分はどこか、という視点でみはじめると、ポジティブな対象にすりかえることができる、というのは有名です。
③自分に都合のよい情報だけを集めようとする
"confirmation bias"です。自分がすでに正しいと思っているものと一致する情報だけを選んだり、そう解釈したりする人間の特性です。英語で言うと、"cherrypick"((悪い意味で)慎重に良いものだけを選ぶ)に相当します。これは2017年に教授が行った実験でも。一旦それが事実だと確信してしまうと、それを裏付ける情報のみに焦点を合わせようとしてしまう、という結果が出ています。
③都合の良い情報だけ集める の対策
決断を下す前に可能性のある原因や説明は吟味してみる。例えば、両親がエンターテイメントビジネスをしている女性が映画などの役を手に入れたとします。その場合、私たちは「親のコネを使ったんだろ」とかんぐってしまいます。それは実際にそういった例が事実としてこれまであったからですね。でも実際はオーディションを受けてそこで結果を出したのでは?違った角度から事実を物事を検証することが重要。
先月実際にあった私のエピソード。電車の隣の座席に座った若いギャルにじ~と見られている。この時、私の中で、「ギャル」「電車内の乗客」という2つのキーワードで過去の体験からバイアスが入ります。「ヘッドフォンの音漏れがうるさいのか」「PCをタイプする音がうるさかったか」「見た目がよくなかったか」。そんなことを思っていたら、突然こちらに近づいてきて「お兄さん肩にてんとう虫ついてますよ」といってとってくれました。助けてくれようとして見ていたっていう角度なんて私にはなかったので、ただただ自分の視野が狭いな、と痛感しました(虫嫌いなのもあり、ギャルが橋本環奈にしか見えず、ドキっとしました)。これは少し違った例かもしれませんが、物事の違った可能性を考えるのは、日頃の思考習慣がないと難しいのではないでしょうか(読書や映画・ドラマが好きな方はこういうのは得意ですよね)。
インタビューのまとめ記事
インタビューをまとめつつ、ライターの視点で認知バイアスについてまとめた記事が同じくNPRで掲載されているので、↓読んでみてください。上述した内容の詳細を英語することができます。
NPRは九州大学など大学入試問題の出典にもなっているため、とても読みやすいと思います。
最後に:決断を下す前には認知バイアスがあることは想定し実行
インタビューを聞いていて、私の72時間ルールは間違っていないということに確信が持てました。とりあえずやってみる、という行動力が結果的に認知バイアスのうち1つを取り除いてくれることがわかったからです。一方で、3つの残りの2つのバイアスは、してしまっている自覚があります。だから、即実行にうつす、というのもを大事だけれど、決めこむ前に、一旦俯瞰してみてみることを重要だなとも感じました。
私は読書や映画・ドラマ鑑賞が大好きなので、他人の気持ちにたってみる、というのは平均よりも上手だ、と自負はしているものの、仕事をしていて、なんでその視点に気づけなかったんだ、なんでオレは人をこういうふうにしか見れないんだ、と自分の見えている世界が狭すぎることに落ち込むことも多々あります。だから、あらためてバイアスに対する対策法、特に「枠組みをひっくり返す」「あらゆる可能性は吟味してみる」、を実践していこう、と思います。
それにしても、MVの"Persona"っていうのがすごいですね。